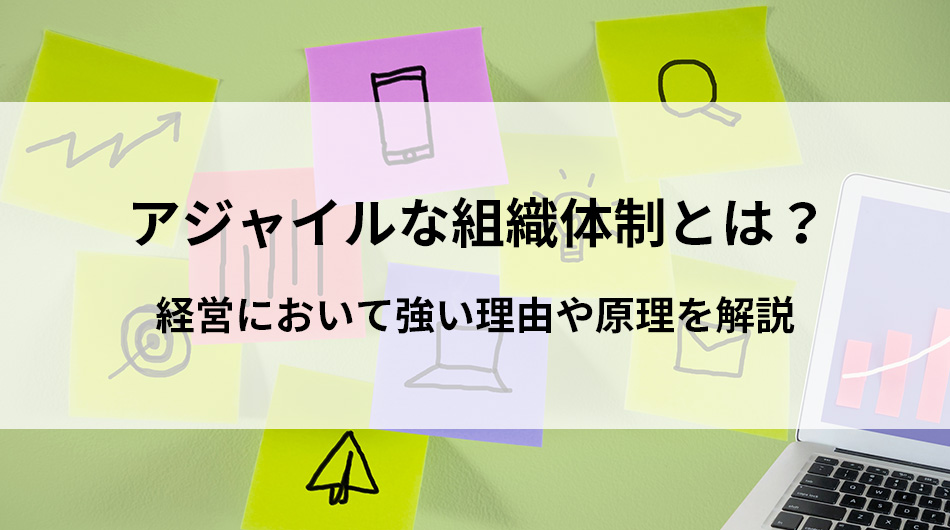バーチャル経営では新規事業を開始するためのベストな組織体制としてアジャイル型の小規模チームを推奨してきました。アジャイル型の小規模なチームは、うまく機能すれば、自動的に新規事業が育つという強みがあります。今回はこの点を含めてアジャイル型の小規模チームがなぜ注目されるかを解説していきます。
アジャイル型組織の根本原理
アジャイルはもともとシステム開発手法のひとつで、「短期間の集中的な開発(スプリント)」と「顧客要望を受けた仕様変更、改善」を繰り返しながら最適なシステムを構築できることが強みです。現在は、システム開発のみならず、経営や組織運営においてもアジャイルが取り入れられ始めています。バーチャル経営では、アジャイル型の組織運営について下記のように定義しています。
自律した人材、裁量と責任の分散、協調の意識
アジャイル型組織に参画するメンバーは、自律型の人材であることが理想です。具体的には、問題提起と改善を自然と行える人材が望ましいでしょう。また、メンバーには一定の裁量と責任を付与し、なおかつメンバー同士が協調の意識を持つことが大切です。こうすることで、個々のタスクが淀みなくスムーズに進み、アジャイルの特長である柔軟性やスピード感が発揮されやすくなります。
メンバーは何かしらの専門家である
アジャイル型組織のメンバーは、それぞれが何かに特化した専門家であるべきです。専門家の集団が、それぞれの知見を出し合い、高いレベルで情報共有を行うことで最適解に行きつきやすくなります。また、常に柔軟な発想のもとにチームを運営するという観点から、参画した時期や年齢などにかかわらずすべてのメンバーが等しく発言権を持つことが理想です。
メンバー同士の結束は比較的固い
アジャイル型組織はタスクやプロジェクトの内容に応じて頻繁に集合や解散を繰り返すことが想定されます。しかし、いわゆるストレンジャー(見知らぬ人、よそ者)が寄せ集められた集団ではないため、結束力を維持しやすいという特長があります。
マネジメントも分散する
アジャイル型組織は従来型の組織に比べるとフラットな構造を持ちます。ただし、マネジメントが不在というわけではありません。むしろチームの中にメンターやアドバイザー的な位置づけの人材を配置することで、マネジメントを細かく分散しつつ、個々の負担を減らすことができます。
責任を分散しつつ「経営者」の意識を広める
上記のようにアジャイル型組織運営の基礎を実践することで、裁量や責任を分散しつつ、すべてのメンバーが自分事として事業に取り組む」文化を醸成することができます。また、全員が事業、ビジネスのオーナー的な視点を得るため、戦略的な視点を常に意識しつつ個々のタスクに取り組むことにつながるでしょう。
ちなみに、バーチャル経営で推奨しているバーチャルチームでも、専門領域が異なる複数の人材をひとつのプロジェクトに集合させ、アジャイル型組織として運営しています。
アジャイル型組織の強み
日本で採用されている代表的な組織構造は、その多くがピラミッドのような階層構造を持っています。一方、アジャイル型組織はリーダーこそ配置されるものの、フラットな構造であることがほとんどです。
フラットであるゆえに情報伝達や意思決定のスピードが速く、少人数であるがゆえに機動力もあります。
中小企業の新規事業は「素早くチャレンジし、見込みがありそうなら継続、無ければ即撤退」といった身軽な行動が必須であり、意思決定スピードやフットワークの軽さに優れるアジャイル型組織が適しているのです。
アジャイル型組織でなければ実現できないこと
アジャイル型組織が注目されている背景には、顧客中心主義の台頭があります。顧客中心主義は、製品仕様やサービス内容を顧客視点でデザインし、顧客満足度の向上を目指すことが要諦です。
この顧客中心主義を実現するためには、顧客要望を随時吸い上げながら製品・サービスに反映させていく体制が求められます。つまり、幾重にも階層が折り重なり意思決定スピードが遅い従来型の組織では対応しづらいのです。
一方、アジャイル型組織ならば、顧客にきわめて近い視点から課題や問題を理解し、随時取り入れながら柔軟に製品・サービスをデザインすることができます。
小さく濃い市場はアジャイル型組織でなければつかみにくい
限定された濃い市場は誕生と消失を繰り返しており、素早い意思決定と見切りがなければ対応しにくいことが特徴です。ABMによって買い手から発見してもらうと同時に、その背後にある限定された濃い市場をつかむには、アジャイル型組織のもつ機動力や柔軟性、専門性が役立つでしょう。
生存戦略の実現
中小企業の生存戦略として注目される「rk戦略」や「ブルーポンド戦略」は、小さな市場や事業の種をいくつも活用し、その中から成功を生み出す仕組みです。これらは、予算やリソースに制限がある中小企業の生存戦略として有望だと考えています。また、「手数」を重視する戦略であるため、小さなアジャイル型組織をいくつも編成して同時並行するという方法が適しているでしょう。
アジャイル型組織の構築に必要なもの
最後に、アジャイル型組織の運営に必要な要素をまとめてみます。
組織モデル
アジャイル型組織のモデルはまだそれほど多くありません。しかし、GAFAでの採用実績もある「The PODsモデル」はアジャイル型組織の運営のモデルになりえると考えています。
従業員の意識改革
もともと日本の組織は、組織の構造はともかくとして、アジャイル型組織に適応しやすい文化があります。特に強調や分散は従来型の組織でも意識されてきたことですし、日本企業の文化とも合致します。ただし、自律(自ら問題を発掘し、解決する力)については小まめに制度改革を重ねながら意識を浸透させるしかないかもしれません。
クラウド型ERP/CRM/SFA
アジャイル型組織は、情報共有のスピード・頻度ともに従来型組織よりも高いレベルを求められるため、ナレッジベースとなるシステムが必須です。独自にナレッジベースを構築するリソースがない場合は、クラウド型ERP/CRM/SFAが持つ機能を活用するのが良いでしょう。ドキュメント管理や案件の進捗状況を手軽に共有できるため、メンバーの情報格差をなくし意思決定の精度を高めることに役立ちます。
総務担当者の8割がアジャイル型組織が必要と回答
総務担当者向けのビジネス情報誌などを運営する「株式会社月間総務」の調査によれば、総務担当者の約8割が「アジャイルが必要」と回答しています。※1
欧米でも同様の傾向があるようですが、日本企業の総務部は欧米よりも職務内容が広汎であり、日本企業の特色が色濃く反映されている部署です。その総務部でさえ、アジャイルへの移行が必要だという考えが広まっているのです。
こうした意識変化の背景には、「変革へのスピード感」「トップダウンの脆弱さ」など従来の日本企業の課題と共通したものがあるようです。日本企業を象徴する部署である総務部がアジャイルの必要性を訴えているということは、アジャイル型組織へ移行すべきときだという証拠なのかもしれません。
反復から本質へ到達するアジャイル型組織
なぜこうした意識変化が起こっているのかを考えると、従来の組織構造の限界が見えてきます。従来の階層構造型組織は、物事を動かす前に本質をつかもうとしていました。アジャイルの対義語として使われる「ウォーターフォール型プロジェクト」がまさにこれで、あらかじめゴール(=システムのあるべき姿)を明確に決めるところからプロジェクトが動き出します。
しかし、このやり方ではゴールが変化し続けるVUCA時代についていくことはできません。
ゴールがわからないならば、とにかく迅速に動き、動き続ける中で柔軟に最適解を見つけていくしかないのです。
アジャイル型組織は、失敗と改善の反復を常とする組織体制であり、この反復の中でゴールを見つけていくことができます。こうしたアジャイル型組織体制の特徴が、現代のビジネスパーソンの心を掴んでいるのかもしれません。
参考:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000060066.html
※1 PR TIMES
アジャイル型組織への移行を成功させるために
アジャイル型組織への移行が順調に進んでいる企業はそれほど多くありません。その理由を探ってみると、日常業務をシステムが足かせになっていることが多いようです。具体的には、業務を支えるシステムが「密結合状態」のままなのです。
日本企業のお家芸だった「オンプレ+密結合な独自システム」が足かせに
従来型の階層構造的な組織構造をもつ企業では、「オンプレミス+密結合」なシステムを採用していました。
具体的には、まずオンプレミス型の基幹システムがあり、これに年次改修や機能追加などを重ね、すべての機能同士を密接に、1:1に近い状態でつなげていくのです。何年も同様のことが繰り返された結果、「一枚岩(モノシリック)で密結合なシステム」が出来上がるわけです。
ただし、これ自体は非難されることではありません。モノシリックなシステムは、変化の少ない階層構造型の組織体制にマッチしています。部署ごとにはっきり業務が分かれていて、要所で連携しながら既存事業を粛々とまわすような状況であれば、何ら問題はありません。
しかし、小規模チームを頻繁に立ち上げ、新規事業にトライするようなアジャイル型組織の場合、こうしたシステムは馴染みません。
カスタマイズやアドオン開発、追加改修を繰り返してきたモノシリック型の密結合なシステムは、ある部門の業務に過剰なまでに特化していることが大半です。また、機能同士の依存関係が濃く、連携先が固定されており、「N:N」で機能が結びついていません。
したがって、頻繁に新しい業務プロセスが発生したり、業務プロセスが変更されたりといった環境についていくことができないのです。
アジャイル型組織には「クラウド+疎結合+アジャイル開発」が必須
つまり、システムを変更せずに組織体制だけをアジャイルにしても、アジャイル型組織の強みを発揮させることはできないのです。
アジャイル型組織とは、「必要な能力(機能)を持った人材を柔軟に結び付け、最適解を見つける」ための組織です。アジャイル型組織に適するのは、汎用的な機能を小さな単位で独立させ、必要に応じて組み合わせる「疎結合なシステム」です。
また、疎結合なシステムを作り上げるためには、汎用的な機能を随時組み合わせながら、徐々に最適解に近づくための開発手法(=アジャイル開発)を根付かせることも大切です。
DXへの近道になりうるアジャイル
アジャイルはもともと、IT業界における開発手法やプロジェクト運営手法として誕生しました。しかし、現代はその枠を超え、組織論としても語られます。
日本企業が向かわざるを得ないDXも、突き詰めれば組織論です。しかし、DXへの実質的な処方箋は無いに等しいのが実情ではないでしょうか。そこで注目すべきがアジャイルであり、アジャイルを支えるシステムなのです。
アジャイル型組織を支えるシステムとは
バーチャル経営では、アジャイル型組織を支えるシステムとして、以下のようなものを想定しています。
クラウド+APIによる疎結合なシステム
クラウドサービスから必要な機能だけを選定し、それらをAPI連携によって疎結合状態でくみ上げます。それぞれの機能は「パーツ」として独立しているものの、「1:1」ではなく、「N:N」で結びつけることを念頭において開発するのです。
「疎結合になることで連携力が落ちるのではないか」という意見もあるでしょうが、機能選定と同時に業務プロセスの標準化も進めれば、大きな問題は生じません。
ローコード開発による「本当に必要とされるシステム」
また、ローコード開発と組み合わせれば、業務担当者が簡易な機能を開発し、クラウドCRMやERPとのAPI連携によって業務に組み込むことも可能です。ローコード開発は近年のIT業界における一大トレンドであり、これから普及が進むと考えられます。
ローコード開発の良いところは「業務担当者が日常的に直面している課題を、自らの手で解決できる」という点です。ローコード開発ツールの多くは、コーディング作業を極力少なくし、直感的に開発が進められるよう配慮されています。プログラミングスキルを持たない人材であっても、頭の中にあるアイディアや要望を簡単に形にすることができるのです。
また、エンジニアやベンダーとのコミュニケーションを省略できるため、認識の齟齬や工数の肥大が生まれにくく、「本当に必要で、つかいやすい機能」が低コストで生み出されます。
もちろん、業務担当者にも一定のITリテラシーは求められますが、エンジニアを調達・育成するコストに比べれば微々たるものです。
外部化で弱点を補う
クラウド+疎結合なシステムの弱点は、個別の機能にかかる運用コストだと言われています。しかし、運用コストは外部化によって抑えることが可能です。何よりも運用員の確保や育成といった問題が生じませんから、外部化は積極的に活用すべきでしょう。
まとめ
アジャイルな組織体制の実現には、それに見合ったシステムが必須です。アジャイルの方法論を組織・システムの両面に組み込むことで、DXへの道が見えてくるかもしれません。DXは「変革に対応できる土壌を作ること」ですが、その前段階として「クラウド+疎結合+ローコード開発」な仕組みは非常に有望であると考えられます。