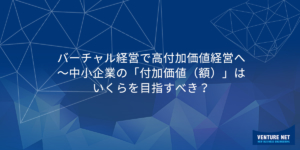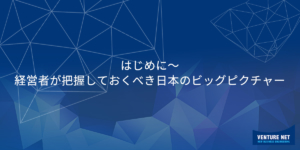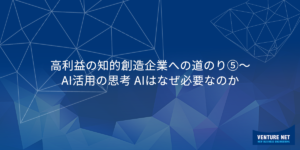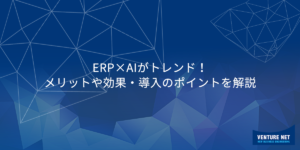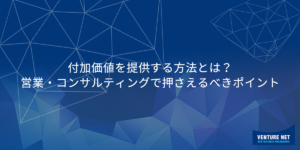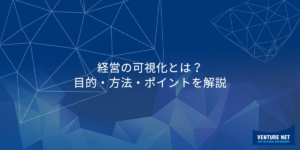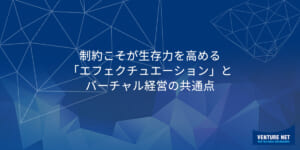「労働分配率」は、「労働者(役員、従業員)に配る”分け前”の割合」を表す指標です。企業の健全性を計測する指標として用いられることが多いでしょう。労働分配率は、コントロールが難しい指標であり、上げすぎても下げすぎてもいけません。従業員のモチベーションを維持しつつ、稼ぐ力も強化するためには、一体どの程度の数値を目指すべきなのでしょうか。
企業と労働者の取り分を決定づける「労働分配率」
まず、一般論としての労働分配率を簡単におさらいしておきましょう。
労働分配率とは何か?
労働分配率とは、「企業が生み出した付加価値の中で人件費が占める割合」です。生み出した付加価値を、給料・福利厚生・役員報酬としてどれだけ分配しているかを示しています。一般的に労働分配率は、次の式で算出可能です。
労働分配率=人件費÷付加価値
ちなみに、付加価値とは「営業純益・人件費・支払利息・動産および不動産賃借料・租税公課」の合計を指します。
また、人件費は「役員報酬・給料賞与・退職給与・法定福利費・福利厚生費・退職年金掛金・賞与引当金繰入額・退職給付引当金繰入額・教育費」などが該当します。
企業規模によって付加価値・人件費は大きな差があり、一般的には企業規模が大きくなるほど労働分配率が低くなっていきます。
企業と従業員の「利益相反」を解決する目安
雇う者と雇われる者の間には、何かしらの「利益相反」が発生します。企業側は生み出した付加価値をできるだけ保存したいと考えます。一方の労働者は、付加価値の中から可能な限り多くの報酬を支払ってもらいたいと考えるのが通常です。片方の利益はもう一方の不利益につながるため、まさに利益相反と言うにふさわしい間柄と言えます。
かつて日本企業は、労使交渉によってこの利益相反を調整してきました。しかし近年は、労組自体が活動しておらず、労使交渉が行われていない企業も珍しくありません。また、労働分配率はこの20年ほど、一貫して下落傾向にあり、企業の取り分が増加しているとも言われています。
しかし、企業側としては年次昇給による人件費の高騰をいかに抑えるかが経営上の重要課題があります。抑えすぎれば従業員のモチベーションは低下し、手綱を緩めすぎれば固定費の増加から身動きがとりづらくなるでしょう。
労働分配率は、労使双方にとってセンシティブな課題である「分け前」を注視し、そのときどきで適切なラインを見極めるための指標なのです。
労働分配率の平均値と目安
ここで、日本企業の労働分配率の平均値と目安を紹介します。前述したように労働分配率は企業規模との相関が確認されており、大企業ほど低く中小企業は高くなるようです。中小企業庁が公開している「2020年度版 中小企業白書」によれば、企業規模別の労働分配率は以下のようになっています。
 出典:中小企業庁「2020年版 中小企業白書(HTML版)」
出典:中小企業庁「2020年版 中小企業白書(HTML版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b2_1_1.html
ピンクの線が大企業、オレンジの線が中堅企業、青の線が小規模企業です。大企業だけが突出して労働分配率が低いことがわかります。2018年度の断面で見ても、「大企業:51.3%」
「中堅企業:76%」「小規模企業:78.5%」であり、大企業とそれ以外の中小企業の間には、実に25%以上もの差が生じているわけです。
あくまでも一般論ですが、「労働分配率は50%程度が適正」と言われています。現状の日本では、大企業のみが労働分配率の適性ラインを維持しており、それ以外の中小企業は「取り分が少ない」と言える状況です。
また、労働分配率の差は営業純益の差にもつながります。これは、中小企業白書で紹介されている下記の図「付加価値に占める営業純益の割合」からも明らかです。
 出典:中小企業庁「2020年版 中小企業白書(HTML版)」
出典:中小企業庁「2020年版 中小企業白書(HTML版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b2_1_1.html
2018年度時点で、付加価値に占める営業純益の割合を企業規模別にみると、「大企業:33%程度」「中堅企業:11%程度」「小規模企業は5%未満」という事実が浮かび上がります。このように、労働分配率が低い大企業ほど営業純益の割合が高いのが実情です。また、営業純益の割合が高い大企業ほど資本力を強化しやすく、中小企業との差は時間の経過と共に大きくなっていきます。
大企業と資本力を競うわけではないにせよ、「効率よく稼ぐ力」は可能な限り近づけておくべきでしょう。
バーチャル経営における労働分配率の目標値
バーチャル経営では、労働分配率の目安を大企業基準の「50%~60%」に設定しています。また、状況の変化に対応するためのマージンとして10%以内の上振れを想定し、「従業員30%、役員報酬20%」程度の分配をイメージします。
さらに、労働分配率を抑制・コントロールするために、これまで紹介した業務廃棄やバーチャル社員を活用することも検討していきましょう。
労働分配率の下げすぎによるリスク
労働分配率は低ければ低いほど良い、という性質のものではないと考えています。過剰な労働分配率の低下は「人材確保の競争優位性」を奪ってしまいかねないからです。簡単に言えば同業他社より給与・待遇が悪くなり、ES(従業員満足度)の低下や離職リスクの増大を招きます。海外の企業に比べると人材の流動性が低い日本であっても、デジタルマーケティングやICTなど、付加価値の高い分野で活躍する人材は簡単に転職してしまいます。
これは、従来型の雇用を前提としないバーチャル社員であっても同様です。バーチャル社員は、「有期雇用契約」「業務請負契約」などを結ぶことが多いため、無期雇用の正社員よりも流動性が高い人材です。特に業務請負契約を結んでいるバーチャル社員は、報酬が高く条件が良い企業との取引にリソースを傾けつつ、簡単にフェードアウトできてしまいます。
したがって、正社員かバーチャル社員かに関わらず、競合他社の労働分配率は可能な限りチェックしておくべきでしょう。帝国データバンクなどの企業向け情報サービスを活用し、労働分配率を上昇させている競合企業が無いかを注視してください。
仮に労働分配率が自社より高い場合は、それがどれくらい続くのか、どういった施策のものとで行われているのかを確認すべきかもしれません。単に経営状況が悪化しているのか、優秀な人材を集めるためにあえて「投資」しているのかで、自社がとるべき対策は変わってきます。
労働分配率を「軟着陸」させるために
労働分配率は、「下げようと思えば下げられる」状態にあるのが理想です。50~60%の間を想定しつつ、徐々にこの10%の幅に「軟着陸」させられる体制を構築しておきましょう。そのためのツールとして、「バーチャル社員」「RPAによる業務廃棄」を活用するわけです。業務廃棄やバーチャル社員活用は、労働生産性(付加価値額)の絶対値を底上げしつつ、従来の働き方・雇い方で生じていたコストを削る効果が見込めます。こうして、人件費は維持もしくは減少させ、付加価値を増大させることで「人件費÷付加価値」の値を小さくし、労働分配率の高止まりを防ぐことが出来るわけです。また、常に自社の労働分配率を可視化するためにCRMやERPなどのデータも注視していくようにしましょう。
まとめ
本稿では、バーチャル経営が推奨する会計的数値のうち「労働分配率」を解説してきました。労働分配率は5~60%を目標としつつ、コントローラブルな状態を目指しておきましょう。次回は、「F/M比率」についての解説です。